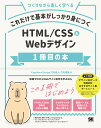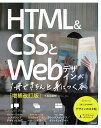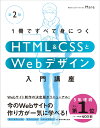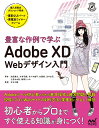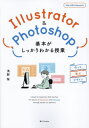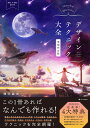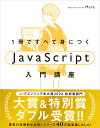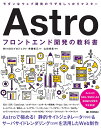目次
はじめに:なぜ本で学ぶのか?
Webデザインの学習方法はさまざまです。
動画講座、オンラインスクール、ブログ記事、YouTube……選択肢が多いですが、本で学ぶことには次のような強みがあります。
- 体系的な流れで学べる(「章立て」「目次」の構造)
- 手元に残る教材として、あとで参照できる
- 著者の思考プロセスや補足説明が文章として詳しく書かれやすい
- 図版・レイアウトで視覚的に理解しやすい
ただし注意点もあります。
Web技術は変化が速いため、古い本だと情報が陳腐化しているリスクがあります。
だからこそ「新版」「改訂版」「最近出版された本」「改訂の頻度」が選書時のチェックポイントになります。
本記事では、あなたが初心者〜中級者レベルから確実にステップアップできるよう、2025年時点でも使える日本語書籍を中心に紹介します。
さらに、将来的に読みたい上級者向け書籍も「番外編」として載せています。
書籍を選ぶ際のチェックポイント
本を選ぶときには、以下の基準を特に重視すると失敗が少なくなります。
| チェック項目 | なぜ重要か | チェック方法 |
|---|---|---|
| 出版年・改訂年 | Web技術(HTML/CSS仕様、ブラウザ挙動、レスポンシブ設計など)は変わるため | “改訂版”かどうか、最新版かを確認 |
| 演習・実践課題の有無 | 手を動かして学ぶことで理解が深まる | サンプルプロジェクト、ワーク付きかを確認 |
| 図版・ビジュアル解説 | 言葉だけでなく視覚的な説明があった方が理解しやすい | 目次・中身を立ち読みして図版の量を確認 |
| レベルの幅 | 自分のレベル感に対応していない本だと挫折しやすい | 「〜入門」「〜応用」などの表記、目次の章構成を確認 |
| 著者・出版社の信頼性 | 実践者による本、技術出版実績がある出版社の本の方が質が高いことが多い | 著者略歴、出版社の技術書実績を見て判断 |
| 読者レビュー | 実際に読んだ人の感想/評価が参考になる | Amazon・書評サイトなどでレビューをチェック |
おすすめ書籍(入門〜中級者向け)
以下は、入門〜中級者向けに特におすすめしたい日本語書籍(2025年時点でも十分使えるもの)です。
書名・特徴・おすすめ対象者を示します。
これだけで基本がしっかり身につく HTML/CSS&Webデザイン1冊目の本
流行り廃りの少ない覚えるべき基本を説明してくれている良書。
2021年発売の書籍だが新品で買ってしっかり書き込んでヘビロテすると良いと思う。
現在、初版第9刷。何気にベストセラー本。
これより簡単な書籍は色々あるけど、仕事にするならこの本のレベルからする方が良いと思う。
図解がしっかりしていて、要所要所に動画のQRがあるから紙面だけじゃ理解が進まないとこのフォローも厚い。
CSSアニメーション、レスポンシブ、Flexboxレイアウト、グリッドなど中級に片足突っ込めるレベルまで網羅している初級書籍。(各説明は必要最低限で応用はないが、理解しやすい説明がついている。)
1冊目の本と書いてあるのは伊達じゃないといった感じ。
デザインの基礎も都度軽くではあるが説明してくれているため、概要を知るにはもってこいの一刷。
大丈夫。ブラウザのインストールとか基本的なとことかもしっかり説明してくれているから問題ない。
特典としてダウンロードコンテンツがある。
- サイトの公開方法(Webサイトをインターネットに公開する方法)
- チートシート4種(Flexbox、CSSグリッド、ショートハンド、キーボードショートカット)
- おすすめサイト集(色相環や素材など)
- サンプルデザイン(カンプデータ)
HTML&CSSとWebデザインが1冊できちんと身につく本[増補改訂版]
2冊目にこの本を選ぶと、内容がしっかり理解できてレベルアップが容易。
最初からコレにいってもいいが、書いてあるままに完走したとしても理解が浅くなると思う。
内容が一歩踏み込んでいて濃い。基礎固めの後に読む入門書。
読み物としても良い。ある程度技術がついてから読み返すと理解がさらに深まる。
この本も2022年発売で第6刷か7刷ぐらいまで出ている。(2024年5月に確認したとき6刷だった。)
1冊ですべて身につくHTML & CSSとWebデザイン入門講座[第2版]
2019-2024年、5年連続、売上第1位。
Web関連の情報やデザインについて記事が学べる『Webクリエイターボックス』の管理人、
Manaさんが執筆した一冊。
プロの現場で役立つテクニック、制作現場の流れといったことがわかる。
とてもためになる本だが、これを最初に持ってこなかったのには訳がある。
きれいなサイトと本の構成過ぎて、蹴躓く可能性があるから。(やる気が削げる)
ある程度知識詰め込んだ後に読むと参考になる。
中級の入り口ぐらいまでできるようになって読むと、非常に役立つ1冊。
自分のおススメというより、これを勧める人が多いため載せたが、上の2冊でHTML&CSSの初級は良いと思う。
HTML&CSS Webデザイン 現場レベルのコーディング・スキルが身につく実践入門
HTML&CSSに関する実践的な知識と、経験の積み重ねのための一冊。
HTML&CSSの最初の学習を完了し、Webサイト制作を仕事にするレベルへと進みたい人用。
実案件をもとに作成した練習サイトを使って制作方法をマスターし、現場レベルのコーディング・スキルを身につけることのできる書籍。
FigmaとAdobe XD両方のデザインデータがついてくるので、両方の練習になって良い。
(世間はFigmaに移行しつつあるが、現状ではAdobe XD、Figma、Photoshop、illustratorなどでデザインカンプを渡されることも多いので、初めのうちから慣れておく方が良いと思う。)
いわゆる「ちゃんとしたコーディング」をするための本。
中級編(全575ページ中、中級編は105ページから)から、JavaScript(jQuery)が入ってくるが、JavaScript部分をスルーしても良いのでしっかり読み込んでやってみると良い。
自分の知識量が試されるので、穴(できてないところ)がわかりやすい。
(こんな方におすすめ)
・HTML&CSSの基本はマスターしたが、自力でWebサイトを作れず悩んでいる人
・HTML&CSSの実務で使えるスキルをマスターしたい人
本書で学べる内容
フレックスボックス/ポジション/グリッドレイアウト/CSSアニメーション/JavaScript(jQuery)/ドロップダウンメニュー/ハンバーガーメニュー/アコーディオン/モーダルウィンドウ/パララックス/スライダー/シングルカラム/2カラム/タイル型/ブロークングリッド/LP(ランディングページ)
これだけの題材のまとまった本がなかったので、自分のサイトページをのせます。
これは必須ツールなので、軽くでも把握していた方が良いです。
Figma、Adobe XD、Photoshop、illustrator
この時点ではさらっと使い方がわかればいいので、基本操作がわかる本をおススメします。
Figmaは触って直感的に覚えれるので、これ一冊でふわっと覚えた後は触ってみるのが早いです。
↑は2025年11月12日発売の一冊ですね。
FigmaだけでWeb制作までできる過程がわかります。
実際はコードを打つにしろ、こういう仕方もあるんだよと知識として持っていると良いと思います。
↑は、2025年12月2日発売の一冊。
手を動かして学べる系の本は基本的にオススメしています。
リアルな制作フローに即して書かれているため、とても勉強になります。
上の本を学んだあと用となりますが、ここに載せておきますね。一冊持っているととてもためになる一冊です。
これ一冊で基本操作を把握して、あとはAdobeのソフトをサブスク契約したらAdobeの無料動画講座が豊富にあるのでそちらで勉強するのが良いと思います。
こちらはインスピレーションを得るのに、良い書籍です。
手元に何ができるかがわかるような書籍が欲しい場合には有用ですが、絶対ではない。そんな感じです。
Webデザイン良質見本帳[第2版] 目的別に探せて、すぐに使えるアイデア集
デザインは普遍的な部分も多いので、古くても読みやすくわかりやすいなら購入OK。
流行りを追い求めるなら、できるだけ新しいものを購入すると良いが、知識が定着した後ならWebサイト検索が一番早い。
2021年発売。項目ごとに分かれているため、ざっと把握するのに適した書籍。
ノンデザイナーズ・デザインブック[第4版]
言わずと知れたノンデザイナーズ・デザインブック[第4版]。
デザインの基本原則を学ぶとともに、わかりやすく美しい図の作り方、図解の効果的なデザイン法、デザイン法則と絡めての使い方が学べる。
微妙に図解などに英語が多いのが難。ビジュアルで理解できるので保存版的に持っていると良いかと。
ノンデザイナーズブックを立ち読みして苦手意識が出る人は・・・
まんがで一通り大切なことはサラッと学べるのでココから始めるのもいいんじゃないかな。
その他のおすすめデザイン書籍+α
この3冊は2024~2025年に発売されたものだから、今のデザインを知れる。
自分に合ったものを買うのも良し、3冊とも買うもよしといったところ。
それぞれ違うので自分は読破後も全部所持している。たまに見ると非常に面白い。
こちらはデザインの本ではないのですが、仕事をするうえで非常に重要になってきたのでさらっと知識として知っておくと良いです。
Webページはきれいなサイトを作ればいいだけの時代から、マーケティングを考えないといけない時代へと変化しています。
中級者向け
1冊ですべて身につくJavaScript入門講座
探してみるとわかるが、Web制作向けのJavaScript書籍は本当に少ない。
その中でも非常にプログラミング初心者にわかりやすく書いてくれているのが、この一冊。
Web制作で使うJavaScriptは技術的には範囲が狭いので最初からWeb制作用に勉強すれば良い。
というか、エンジニア用のJavaScript本で勉強すると挫折すると思う。
後々、バックエンドの実装するときに難しいのを読むという流れが安心安全。(基礎ができているだろうし。)
CSSとJavaScriptで作る動くUIアイデアレシピ
知りたいことがさっとわかる一冊。
CSSで現在できることの範囲も再確認できる。
一冊持っておくと調べる時間の短縮になります。
あと、読みやすいです。
各本の使い方・読み進め方の工夫
ただ本を読むだけでは定着しにくいため、以下のような方法を組み合わせて学習を進めると効果的です。
- 章ごとに読む → 手を動かす演習をする
読むだけで終わらせず、演習プロジェクト・サンプルコーディングを必ず行う。 - 模写・再現演習
「見本サイト」を模写して作ってみる。見本帳(例:『Webデザイン良質見本帳』など)が特にこの用途で役立つ。この時、最初は本やコードを見て構築してみて、次は極力見ずに行い、最後は何も見ず(カンプは見てね)にコーディングすると力が付きやすく、自分が苦手な領域も把握しやすいです。 - アウトプットしてみる
自分のポートフォリオサイトやブログを使って、学んだ知識を実際に適用してみる。 - 復習・参照用ツールとして活用
図版・目次が整った本は、後から参照するのにも使える。困ったときにすぐページを開いて確認できるように。 - 並行学習で補強
HTML/CSS を学びつつ、デザイン理論(配色、レイアウト、タイポグラフィ等)の本も並行して読むと理解が深まる。
学習ロードマップ:ステップ別の進め方
以下は、未経験者が「ステップ1 → ステップ2 → 実践プロジェクト」へと進むためのロードマップ案です。
| ステップ | 目標 | 推奨書籍 | 学習内容 |
|---|---|---|---|
| ステップ 0(準備) | Web デザイン全体を俯瞰する | 『1冊ですべて身につく HTML & CSS と Webデザイン入門講座[第2版]』 | Web デザインの流れ・役割・技術要素の全体像を理解 |
| ステップ 1 | HTML / CSS の基礎を習得する | HTML&CSSとWebデザインが1冊できちんと身につく本[増補改訂版] | HTML 要素・CSS 基本プロパティ・レイアウト技法を学ぶ |
| ステップ 2 | レイアウト応用・実践コーディング | 『HTML&CSS Webデザイン:現場レベルのコーディング・スキルが身につく実践入門』 | Flexbox / Grid / レスポンシブ設計 / 実務的なコーディング手法 |
| ステップ 3 | デザイン表現力を高める | 『Webデザイン良質見本帳』+模写演習 | 実際の Web デザインを素材として解析 → 自分で再現 |
| ステップ 4 | 実務プロジェクトへ展開 | SEO・自作サイト・クライアント案件等 | デザイン → コーディング → 公開・運用 → ブラッシュアップ |
この方式で進めていけば、「ただ読んで終わる」ではなく、「使えるスキルを身につける」レベルに近づきます。
番外編:上級者向け・専門テーマの書籍(補足)
基礎・中級レベルをクリアしたら、さらに深堀りしたいテーマ向けの書籍もあれば読んでおきたいです。
以下はその例です。
UI/UX デザイン理論 / プロセス系
オブジェクト指向 UI デザイン、ユーザー中心設計、インタラクション設計などを扱う本。
実務設計力を高めたい人向け。
モダン CSS / JavaScript / フレームワーク
最新 CSS(変数、カスタムプロパティ、Flexbox / Grid 応用)、モジュール設計、Vanilla JS / React / Vue 等を扱う本。
個人的に、最初のフレームワークやサーバーサイド、バックエンド言語を勉強する前に読んでほしい一冊です。
Javascript派生でWebサーバーの作成などもできるんだよーっていう本です。
データベースも扱っているので、まずはコレ読んで自分の方向性を決めるといいかなと思います。
最近のWeb制作現場で徐々に存在感を出しているのがAstroです。
Astroは「できるだけJSを使わずに、軽くて速いサイトを作る仕組み」です。
JSが必要なところだけ自動で最小限に変換・配信してくれるので読み込み速度が速く、SEOに強みがあります。
Web アニメーション / モーションデザイン
スクロールアニメーション、遷移効果、SVG アニメーションなどを扱う本。
After EffectsもAdobeで習えるので基本はそちらでOK。この本は何ができるかをザッと知るために有用です。
パフォーマンス/アクセシビリティ/SEO 専門
パフォーマンス最適化、アクセシビリティ設計、SEO 対策を深く学びたい人向け。
おそらくすべてのHTML&CSSが書いてあります。細かいところまで。辞書ですね。
若干古いですが、SEOの歴史と基本的な考え方が学べます。
こちらは最新のAI検索などに対応した書籍です。
まとめ:着実にスキルを伸ばすために
- 最初は 入門〜中級者向けの本 を一冊+見本帳などを併用して進める
- 演習・模写・アウトプット を必ず組み込むこと
- 必要に応じて 上級テーマ書籍 を番外編的に取り入れる
- 定期的に 改訂版・出版年 をチェックして、古い知識にならないよう更新する
- スクールがオススメだが、独学するにしろ情報収集は必ず必要。最先端の情報はスクールの無料カウンセリングが一番近道。