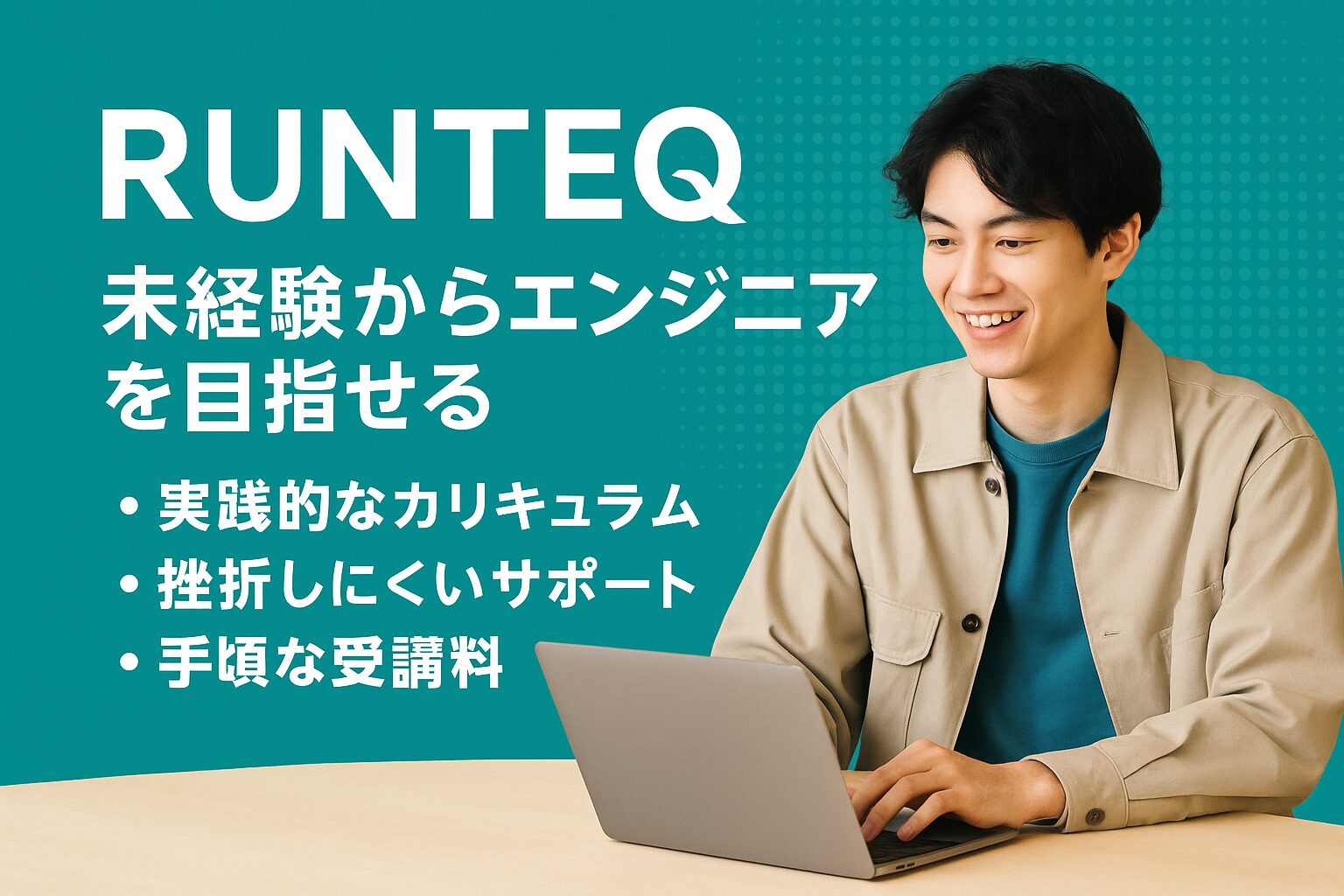Rubyはプログラミング初学者にとってデバックがしやすく、シンプルで読みやすい文法が特徴のプログラミング言語で、初学者にもとっつきやすい言語です。
ここでは、Rubyの基本的な構文や概念について、11の項目に分けて簡単に説明します。
プログラミング初心者でも理解しやすいよう、具体例を交えながら説明していきます。
目次
01 変数編
Rubyでは、変数を使ってデータを保存し再利用できます。
変数は型を指定せずに使用できるのが特徴です。
greeting = "こんにちは"
age = 25
is_student = true
変数名は小文字またはスネークケース(例: user_name)で始めるのが一般的です。
02 定数編
定数は一度定義したら変更しない値です。
Rubyでは、変数名を大文字で始めると定数になります。
TAX_RATE = 0.1
定数も変更はできますが、警告が出るので注意しましょう。
絶対に変更不可としたい場合は、freezeメソッドというものを使うこともできます。
03 真偽値編
真偽値(Boolean)は、true(真)またはfalse(偽)の2つだけです。
また、nilも偽として扱われます。
is_raining = false
puts "傘を持っていこう" if is_raining
条件分岐の際に活躍します。
04 配列編
配列は複数の値をまとめて扱えるデータ構造です。
fruits = ["りんご", "バナナ", "みかん"]
puts fruits[0] # => りんご
添字(インデックス)は0から始まります。
ちなみに後ろから数える場合は-1から始まります。
インデックスを指定して取得する場合は[ ]を使います。
puts fruits[0] #りんご
要素の追加はpushを使います。
fruits.push(“なし”)
05 ハッシュ(連想配列)編
ハッシュはキーと値の組み合わせでデータを管理します。
下のコードで言うと、name:がキー、”太郎”が値です。
person = { name: "太郎", age: 20 }
puts person[:name] # => 太郎
シンボル(:nameのような形式)をキーとして使います。
06 演算子編
Rubyでは算術演算子(+、-、*、/、%)や比較演算子(==、!=、>、<)などが使えます。
x = 10
y = 3
puts x + y # => 13
puts x > y # => true
文字列の結合にも + を使えます。
07 条件分岐編
条件に応じて処理を分けるにはif、elsif、elseを使います。
score = 85
if score >= 90
puts "優秀"
elsif score >= 60
puts "合格"
else
puts "不合格"
end
シンプルな条件は1行で書くこともできます。
08 繰り返し編
繰り返し処理にはfor、eachやtimes、whileなどがあります。
3.times do
puts "こんにちは"
end
fruits = ["りんご", "バナナ"]
fruits.each do |fruit|
puts fruit
end
反復処理はRubyの得意分野の一つです。
3.times は、do...end ブロック内の処理を3回繰り返します。
実際のRubyやRuby on Railsのプロジェクトにいると、ほぼfor inは見ない印象があります。
どちらかというとeachを利用するケースが多いです。
09 メソッド編
メソッドは処理のまとまりを定義する方法です。
def greet(name)
puts "こんにちは、#{name}さん"
end
greet("花子")
引数や戻り値を使って柔軟に処理を組み立てられます。
10 クラス編
Rubyはオブジェクト指向言語であり、クラスを使ってオブジェクトを定義します。
class User
def initialize(name)
@name = name
end
def say_hello
puts "こんにちは、#{@name}さん"
end
end
user = User.new("太郎")
user.say_hello
@nameのような変数はインスタンス変数と呼ばれます。
@を深堀すると、
| num = 100 | ローカル変数 |
| $num = 100 | グローバル変数 |
| @num = 100 | インスタンス変数 |
| @@num = 100 | クラス変数 |
※コードを読むときの参考までに
11 モジュール編
モジュールは、複数のクラスで共有する処理をまとめる仕組みです。
module Greetable
def greet
puts "こんにちは"
end
end
class Person
include Greetable
end
person = Person.new
designer.greet
includeを使ってモジュールの機能をクラスに取り込めます。まとめ
以上が、Rubyの基本的な構文と概念です。
これらの要素を組み合わせることで、より実用的なスクリプトやアプリケーションを作成できます。
次のステップとしては、実際に手を動かして簡単なプログラムを書いてみることをおすすめします。
どの言語にも言えることですが、完璧を目指すといつまでたっても次のステップに進めないので(というか、完璧に覚えている人って一握りいるかいないかだと思う)、最初の内はざっくりで良いと思います。
ある程度こなしたらRuby on rails(フレームワーク)に歩みを進めましょう。
資格もあるので、それを目指すのも良いと思います。
Ruby Association Certified Ruby Programmer Silver version 3
をまずは目標にすると良いかと。
上位資格のRuby Association Certified Ruby Programmer Gold version 3というのもあるのですが、業務ではまず使わないだろそんなもんって内容の問題が多く、こちらは趣味の領域になってきます。
突き詰めて勉強したい!!っという意欲的な人か、もしくは資格マニア用だと思っています、個人的に。