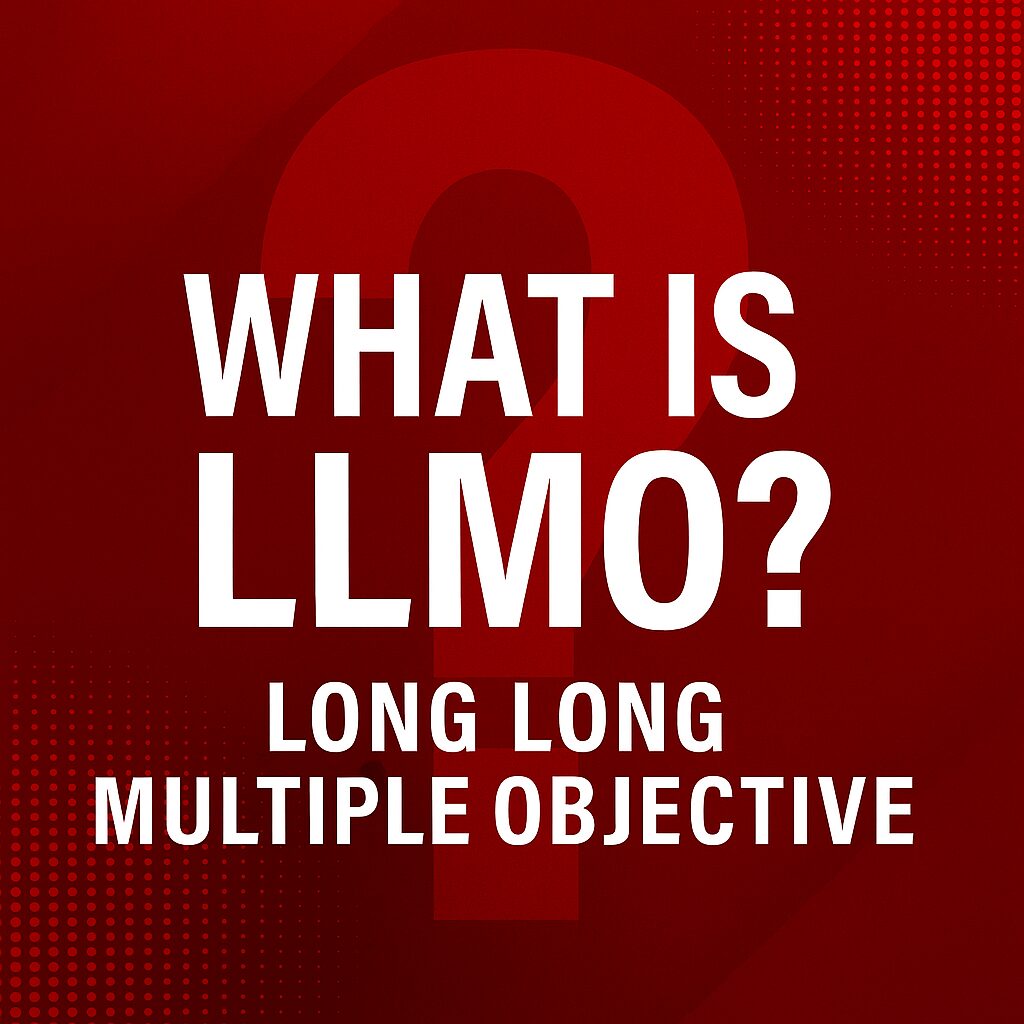検索からの流入は、今でも一番「本気度の高い人」を連れてきてくれる導線です。
SNSでなんとなく見かけた人より、「いまそれを知りたい」と思って検索した人のほうが行動に近いからです。
ところが今のGoogleは、ユーザーがページを開く前に答えを返すようになってきました。
つまり、これからは「検索で上にあるか」だけでなく「その答えの中に入れてもらえるか」まで考えないと、見つけてもらえない場面が増えていきます。
この記事では、その前提でのSEO→AEO対応の考え方を整理します。
目次
なぜ検索流入はいまだに重要なのか
ユーザーは何かを調べるとき、いまでも最初に検索を使います。
検索結果の上に出た数サイトがほとんどのクリックを集め、それ以外は見られません。
しかも検索から来る人は「いま必要な情報を探している」ので、商品ページや問い合わせフォームまで進んでくれる確率が高くなります。
ここで見つからないということは、そもそも検討の土俵にすら乗らないということです。
✔︎ポイント
・検索は今も「買う前・申し込む前」の起点
・ここで出なければ、他のチャネルの成果も伸びにくい
Googleが“答えを返す検索”になったことの意味
最近の検索結果は、AIが内容をまとめて最初に表示し、下にオリジナルのページが並ぶ形が増えています。
これはユーザーにとっては便利ですが、サイト運営側からすると「クリックされる前に完結される」リスクです。
これまでのように「1ページ目にいればなんとかなる」という発想だけだと、露出量が足りなくなります。
✔︎ポイント
・これからは「どの位置に出るか」ではなく「答えに採用されるか」が重要
・AIが拾いやすい書き方をしているサイトが有利になる
SEOからAEOへ:何が違うのか
従来のSEOは「このキーワードで上位に出す」ことが中心でした。
AEO(Answer Engine Optimization)は、AIや検索エンジンが答えをつくるときに使いやすいように、情報の形を整える考え方です。
つまり「人にだけ分かればいい文章」ではなく、「機械にも分かる形」にしておく必要があります。
ここで効いてくるのが、質問形式の見出しやFAQ、構造化された情報です。
✔︎ポイント
・H2/H3に「〜とは?」「〜するには?」を入れる
・ページ内にQ&Aブロックを置く
・誰が・いつ書いたかを明示する(E-E-A-T)
AEO時代でも変わらない“土台のSEO”
「AIが答えるならSEOは要らないのでは?」と思いがちですが、実際は逆です。
AIが答えを組むときの材料は、結局ウェブ上のページだからです。
ページがインデックスされていなければ材料にもなりませんし、表示速度やモバイル対応が甘いサイトは評価が下がります。
なのでこれまでの技術的SEOは、引き続き最初にやっておくべき土台です。
✔︎ポイント
・モバイルで崩れないこと
・表示速度を落とさないこと
・サイトマップとrobots.txtを整えておくこと
・canonicalで重複をなくすこと
記事の書き方をどう変えるか
ここからが実務に一番効く部分です。
AEOを意識するなら、記事を次のような順番で組みます。
- いきなり結論を書く
- その理由をH2で分ける
- 質問に答える形のH2/H3を並べる
- 一番下にFAQ的な短文Q&Aを置く
- 更新日と著者を明記する
こうしておくと、冒頭でAIに拾われやすくなり、下のほうでユーザーの個別の疑問もカバーできます。
特に「SEOをやらないとどうなるか?」「AEOとSEOの違いは?」のような、そのまま質問になりそうな見出しは入れておいたほうがいいです。
✔︎ポイント
・最初の3〜4行に答えを書く
・見出しを“会話っぽく”する
・1セクションを長くしすぎない(300〜500字程度)
よくある3つの失敗
- 上位にある記事をマネして、質問に答えていない
- 誰が書いたか分からないのでE-E-A-Tが伝わらない
- 更新日が古く、AIに「鮮度が低いコンテンツ」と見なされる
この3つは、いまのGoogleで目立たない原因になりやすいです。
特に2025年時点では“鮮度”が想像より重く見られているので、半年に1回は見直す前提で設計したほうが安心です。
競合との差がつくところ
上位のサイトは、コンテンツの数を増やすだけでなく「どの質問で表示されたいか」をかなり細かく決めています。
さらに構造化データ(FAQやHowTo)を入れておくことで、AIや検索エンジンが意味を取りやすくしているケースが多いです。
逆に言えば、この部分をやっていない中小サイトなら、ここだけでも一気に差がつきます。
✔︎ポイント
・“記事を増やす”より“質問を埋める”と考える
・構造化データは面倒でも入れておく
今やらないと何が起きるか
SEOやAEOは“貯まる施策”です。
早く始めたサイトが、トピックに関する情報を長く出しているぶんだけ有利になります。
着手が遅れると、AIに「このテーマならこのドメイン」と覚えてもらうまでの時間が長くなり、追いつくコストが上がります。
つまり後回しにするほど、広告に頼らざるを得ない期間が長くなるということです。
まとめ:これからの基本型
- 検索は今も最優先の導線。無視はできない
- ただし「1位を取る」だけでは足りず「答えに入る」ことが必要
- そのために、質問形式の見出し・FAQ・構造化・E-E-A-Tをそろえる
- 技術的SEOは引き続き土台として必須
- 後回しにすると競合が先に“答えの枠”を取ってしまう
よくある質問(FAQ)
Q1. AEOってSEOと何が一番違いますか?
A. SEOは「ページそのものを上位に出す」発想、AEOは「検索やAIが答えをつくるときに材料にしてもらう」発想です。なのでAEOでは質問文の見出し・FAQ・構造化データがより重要になります。
Q2. 先にやるべきなのは技術的SEOですか?コンテンツですか?
A. 表示速度やモバイル対応など“致命傷になりやすいもの”は先に直してください。そのうえでコンテンツをAEO対応にします。
Q3. 既存記事もAEO対応にしたほうがいいですか?
A. したほうがいいです。とくにアクセスがある記事ほど、末尾にQ&Aを足す・見出しを質問形に直すだけでも拾われやすくなります。
Q4. 構造化データは必須ですか?
A. “必須”ではないですが、AIやGoogleに「ここが答えです」と伝えやすくなるので、FAQPageやHowToはできるだけ入れておくと有利です。
Q5. どれくらいの頻度で更新すればいいですか?
A. 半年に1回は“情報が古くなっていないか”を見るのをおすすめします。変化が速い分野なら3か月に1回が安心です。