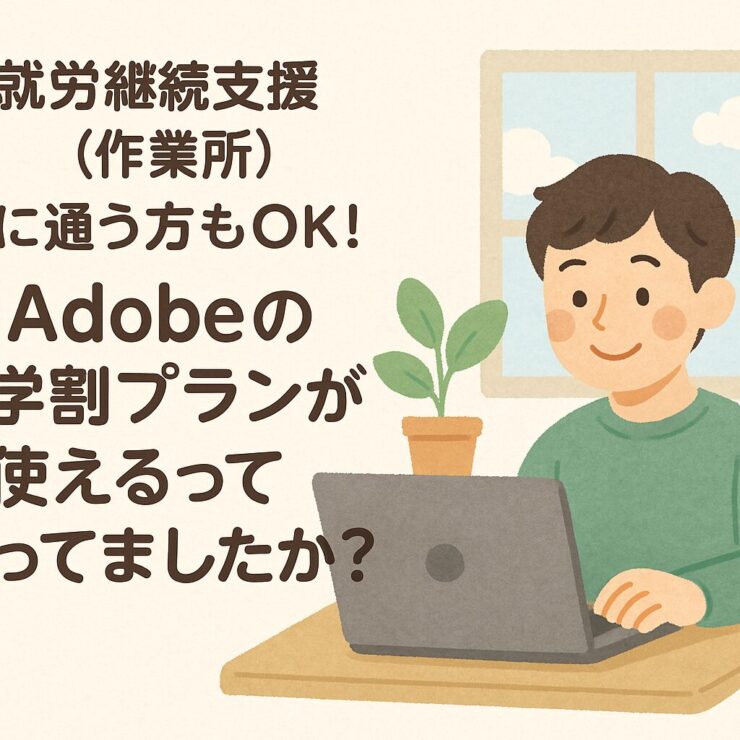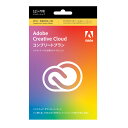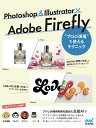目次
「Adobeの学割」って、学生だけの特権じゃなかった!
Adobe Creative Cloudといえば、PhotoshopやIllustratorなど、クリエイティブな仕事に欠かせないツールがそろったサービスです。
でも、月額料金が高くてなかなか手が出しづらい…と感じている方も多いのではないでしょうか。
そんな中、とってもお得なプランがあるんです。それが 「学生・教職員版プラン」
なんと、通常価格より69%OFFという圧倒的な割引率!
そして実はこの学割、就労継続支援A型・B型(いわゆる「作業所」)に通っている方も対象になるんです。
「えっ?作業所って学生じゃないのに?」
そう思った方にこそ、ぜひ知ってほしい内容です。
作業所利用者も学割対象になる理由とは?
Adobeが提供している「教育機関向けライセンスの対象一覧表」という資料があります。
その中にこんな記載があります。
「障害者総合支援法に基づく就労移行支援事業所および就労継続支援事業所」
つまり、就労継続支援A型・B型事業所も、Adobeが認める“教育支援機関”のひとつとしてカウントされているんです。
これはあまり知られていない情報なので、フリーランスや副業でデザインを始めたいと思っている方にとって、かなり嬉しい話ではないでしょうか?
気になるお値段は?【最新価格情報】
Adobeのコンプリートプラン(全アプリ使い放題)の学割価格は以下の通りです。
| 年数 | 月額(税込) | 年間合計(税込) | 割引率(通常9,080円/月と比較) |
|---|---|---|---|
| 初年度 | 2,780円 | 33,369円 | 69%OFF |
| 2年目以降 | 4,180円 | 50,160円 | 53%OFF |
※2025年8月6日時点の価格です。
初年度は特に破格です。
収入が限られている方でも手が届きやすく、「やってみたい」を形にするチャンスが広がります。
購入手続きの流れと必要なもの
「学生・教職員版プラン」を選択して購入を進めると、以下のようなステップがあります。
- 購入方法を選ぶ
月々払いでも一括払いでも、トータルの金額は変わりません。 - 情報を入力
・氏名や連絡先
・支払い方法
・通っている就労支援事業所の名称や利用期間など - 証明書を提出
Adobeから「証明書を提出してください」というメールが届きます。作業所の場合、「障害福祉サービス受給者証」や「契約書」などに記載された就労継続支援の利用情報をスマートフォンで撮影し、画像をアップロードすればOK。学生証の代わりになります。
※特に連絡がない場合もあるようです。
他にもこんな施設が対象になっています
就労継続支援事業所以外にも、以下のような機関に該当していれば、同じく学割が利用できます。
教育機関・公共施設などの例
| 幼稚園・保育所・小学校〜大学までの各種学校 |
| 特別支援学校や高専、インターナショナルスクール |
| 教育委員会およびその施設 |
| ハローワークが斡旋する求職者支援訓練施設(3ヶ月以上) |
| 職業能力開発施設・職業リハビリセンター |
| 視覚障害者支援施設や盲導犬訓練施設など |
| 独立行政法人やNPO法人で認定を受けた教育支援機関 など |
※詳しくはAdobe公式サイトで最新情報をご確認ください。
通所していなくても学割を受けられる方法も?
もし「どの機関にも該当しない…」という場合でも、アドビスクールパートナー認定校が提供するオンライン講座を受講すれば、学割価格でCreative Cloudを使える場合があります。
たとえばデジハリオンラインさんの、Adobeマスター講座(68,800円税込)

ヒューマンアカデミーさんのAdobeベーシック講座(68,800円税込)
オンラインで学びながら、同時にお得な価格でツールも手に入れられるというわけですね!
※他にも一件見つけたんですけど、教材が古かったのでオススメに挙げていません。
まとめ|作業所に通いながら、夢に近づける一歩を
就労継続支援A型・B型事業所に通っている方でも、Adobeの「学生・教職員版プラン」を利用できるのは、あまり知られていないけれどとても大きなメリットです。
月2,780円という価格なら、フリーランスや副業としてデザインにチャレンジしたい方にもぴったり。
自宅で少しずつ始めてみることで、自分の世界や可能性が広がっていくかもしれません。
ぜひこの制度を活用して、あなたの「やってみたい」を実現してください。
必要に応じて、申請や証明書の準備について事業所スタッフと相談しながら進めるとスムーズです。
分からないことがあれば、Adobeのサポートにも問い合わせてみましょう。
ちなみにAmazonさんや、楽天さんでも学割プラン商品を売っておられますが少し割高です。時々安いのが出てくるようなので、たまにチェックするのも良いかもしれませんね。
個人的にオススメなAdobe本のリンクもいくつかのせておきます。