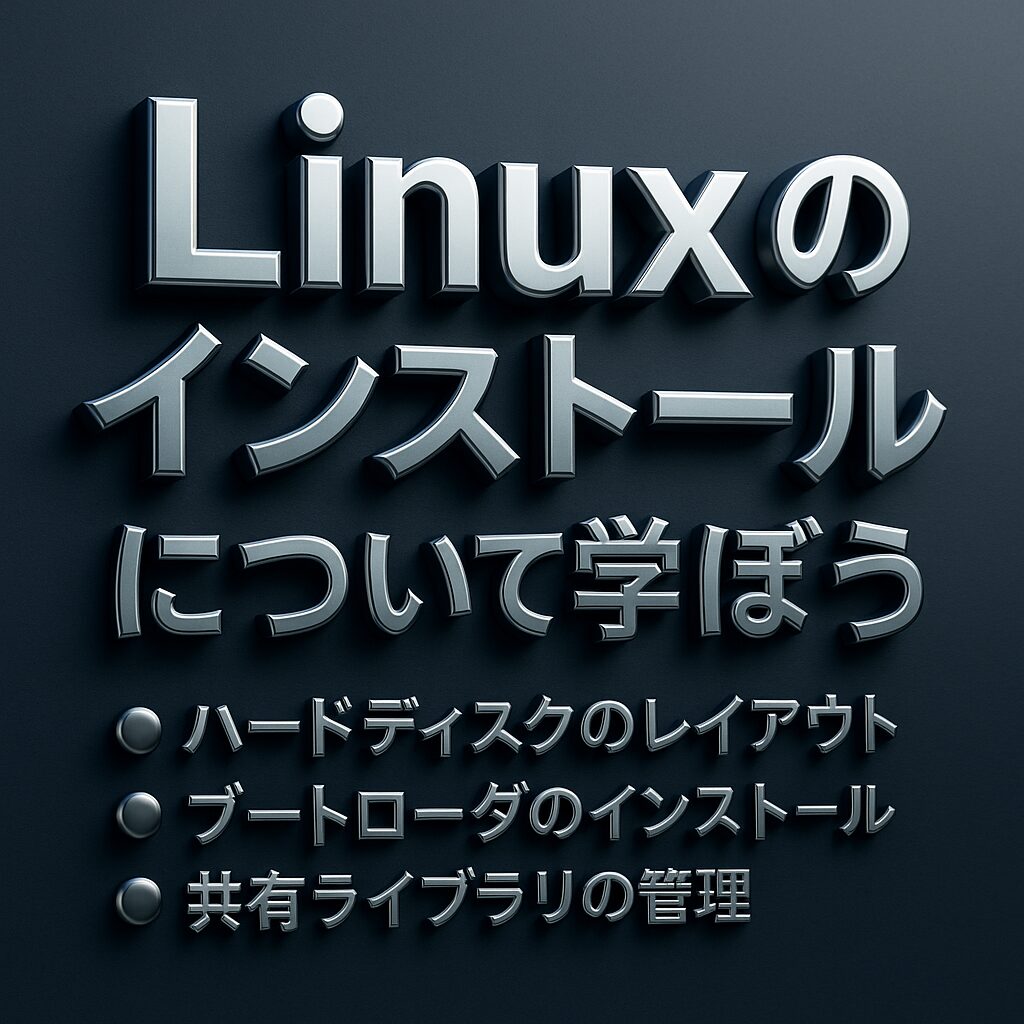AWSには200以上のサービスがあり、何がどの役割を持っているのか混乱しやすいですよね。
特に初心者にとって 「EC2 と Lambda の違いは?」
「RDS はどの分類になるの?」 といった疑問がつきものです。
そこで本記事では、AWSサービスの理解に必須となる “サービスの提供範囲” と
“IaaS / PaaS / SaaS の分類” をまとめて整理します。
この2つをセットで覚えることで、サービス同士の関係性が一気にクリアになり、
設計・学習・資格試験の理解がとてもスムーズになります。
目次
① 代表的な AWS のサービスとその提供範囲
AWS を扱ううえで必ずおさえたい主要サービスを、カテゴリ別に一覧表にまとめました。
それぞれ「何をするサービスなのか?」がすぐわかる構成になっています。
| カテゴリ | 主なサービス | 役割・できること(初心者向けの説明) |
|---|---|---|
| コンピューティング(計算処理) | EC2(Elastic Compute Cloud) | 仮想サーバーを起動して、アプリやWebサイトを動かせる。パソコンの「頭脳」にあたる部分。 |
| Lambda | サーバーを用意せず、コードだけ実行できる「サーバーレス」な仕組み。使った分だけ課金される。 | |
| ECS / EKS | コンテナを使ったアプリ実行環境を管理。複数のアプリをまとめて効率よく動かせる。 | |
| ストレージ(データ保管) | S3(Simple Storage Service) | 画像や動画、バックアップなどを保存できるクラウド上の「倉庫」。耐久性が非常に高い。 |
| EBS(Elastic Block Store) | EC2に接続するディスクのようなもの。サーバーと一緒に使う記憶装置。 | |
| EFS(Elastic File System) | 複数のEC2で共有できるネットワーク型のファイル共有ストレージ。 | |
| データベース | RDS(Relational Database Service) | MySQL・PostgreSQL などのデータベースを簡単に構築・運用できる。管理はAWSが代行。 |
| DynamoDB | 高速・スケーラブルな NoSQL データベース。アクセスが多いアプリに強い。 | |
| Aurora | RDSよりも速く、可用性の高いAWS独自のリレーショナルデータベース。 | |
| ネットワーク | VPC(Virtual Private Cloud) | AWS内に自分専用のネットワーク空間を作れる。仮想のLANのようなもの。 |
| Route 53 | DNS(ドメインの住所管理)サービス。WebサイトのURLを正しいサーバーへ導く。 | |
| CloudFront | 世界中にデータをキャッシュして、高速配信するCDN(コンテンツ配信ネットワーク)。 | |
| セキュリティ・アイデンティティ管理 | IAM(Identity and Access Management) | ユーザーや権限を管理するサービス。「誰がどこまで使えるか」を細かく設定可能。 |
| KMS(Key Management Service) | データの暗号化鍵を管理。セキュリティ強化に必須。 | |
| WAF(Web Application Firewall) | Webアプリを外部攻撃から守るファイアウォール。 | |
| 監視・運用管理 | CloudWatch | AWS全体の動作やリソースを監視。異常があればアラートを出せる。 |
| CloudTrail | 誰がいつどんな操作をしたかを記録する監査ログサービス。 | |
| Config | AWSリソースの設定変更を追跡して、構成管理を行う。 | |
| アプリケーション統合 | SNS(Simple Notification Service) | メール・SMS・プッシュ通知などを自動送信する仕組み。 |
| SQS(Simple Queue Service) | メッセージを一時的にためて、順番に処理するための「キュー」システム。 | |
| API Gateway | 外部サービスやアプリと連携するための入り口(API)を簡単に構築できる。 | |
| 開発・デプロイ支援 | CodeCommit | AWS上で使えるGitリポジトリ。ソースコードのバージョン管理ができる。 |
| CodeBuild / CodeDeploy | アプリのビルド・テスト・デプロイ(配信)を自動化。CI/CDの仕組み。 | |
| CloudFormation | AWSの構成をテンプレート化して、自動的に環境を構築できる。 |
覚え方ポイント(初心者向け)
- EC2 / S3 / RDS は AWSの三大サービス(まずこの3つを覚える!)
- VPC + IAM は「安全に守るための土台」
- CloudWatch / CloudTrail は「見張り役と記録係」
- Lambda / API Gateway / DynamoDB の組み合わせは「サーバーレス構成の鉄板」
② AWSサービスを IaaS / PaaS / SaaS で整理する
AWS を理解するもう1つの重要ポイントが、
「そのサービスが IaaS / PaaS / SaaS のどれに分類されるか?」 です。
この違いをつかむことで、設計思想が一気に明確になります。
一覧表
| 区分 | AWSサービス | 役割・特徴(初心者向け) |
|---|---|---|
| IaaS(インフラを提供) | Amazon EC2 | 仮想サーバーそのもの。OSから自由に構築できる。 |
| Amazon EBS | EC2に付けるストレージ(ディスク)。 | |
| Amazon VPC | 自分専用のネットワーク空間を作るサービス。 | |
| Elastic Load Balancing | サーバーへのアクセスを分散する装置。 | |
| Amazon S3(※分類上はIaaS寄り) | 画像・動画・バックアップなどを保存するストレージ。 | |
| PaaS(アプリ実行環境を提供) | AWS Lambda | サーバー不要でコードだけ実行できる環境。 |
| Amazon RDS | データベースをAWSが管理してくれるマネージドDB。 | |
| Amazon Aurora | 高速で可用性の高いAWS独自のDB。 | |
| Amazon ECS / EKS | コンテナを動かす環境(管理をAWSが担当)。 | |
| AWS Elastic Beanstalk | アプリをアップロードするだけで環境構築が完了。 | |
| API Gateway | APIを簡単に作れるフルマネージドサービス。 | |
| AWS Batch | バッチ処理を効率的に実行するPaaS系サービス。 | |
| SaaS(アプリとして使うサービス) | Amazon WorkMail | AWS版メールサービス。すぐ使える。 |
| Amazon WorkSpaces | 仮想デスクトップサービス。PC環境をクラウドで提供。 | |
| Amazon Chime | オンライン会議ツール。すぐ使えるSaaS。 | |
| Amazon QuickSight | BIツール。グラフ分析を即利用できる。 | |
| Amazon Connect | コールセンターをすぐ構築できるサービス。 |
補足:AWSは「IaaSとPaaSの中間」が多い
AWSにはいわゆる“純粋な SaaS”は少なく、
多くのサービスは「IaaS よりの PaaS」または「PaaS よりのマネージドサービス」という立ち位置です。
そのため AWS 学習では次の理解が重要です👇
- EC2 / VPC / EBS = IaaS の代表
- RDS / Lambda / ECS = PaaS(= マネージドサービス)
- WorkSpaces / WorkMail など一部が SaaS
もっと覚えやすくまとめると
- IaaS = 土台。サーバー・ネットワークそのもの
- PaaS = 料理をする“キッチン”。食材(アプリ)をすぐ調理できる
- SaaS = 料理が完成してテーブルに出されている状態
AWSは “キッチン(PaaS)” が多いクラウド と覚えると理解しやすいです。
まとめ:この2つをセットで覚えるとAWSが一気に理解できる
AWSを学ぶうえで最初に迷うポイントは
「サービスの役割」「分類」「境界線」の3つです。
この記事で紹介したように、
① 提供範囲の整理(どのカテゴリのサービスか)
② IaaS / PaaS / SaaS の分類(どの階層をAWSが管理してくれるか)
この2つをセットで学ぶと、サービス全体がすっきりと理解できます。
特に初心者は次を覚えるとスムーズです👇
- EC2 / S3 / RDS / VPC をまず押さえる
- Lambda・API Gateway・DynamoDB はサーバーレス三種の神器
- IaaS → PaaS → SaaS の順で「管理する範囲が減っていく」
AWSの学習や資格試験、そして実際の設計でも大きな強みになります。