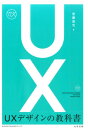目次
なぜ今「UX」が注目されるのか?
近年、デジタル社会の急速な発展によって、企業のマーケティング活動は大きな変革を迫られています。
かつては「広告で集客し、製品を購入してもらう」ことが中心でしたが、今はそれだけでは不十分です。
ユーザーが製品やサービスを実際に利用する過程や、そこから得られる満足度や感動体験こそが企業価値を決める時代となりました。
これを包括的に表す概念が UX(User Experience:ユーザー体験) です。
本記事では、UXの定義や人間中心設計のプロセス、なぜ重要になっているのか、そして企業事例を交えながら詳しく解説します。
UXとは何か?
UXとは、ユーザーが製品やサービスを通じて得られる体験の総体を意味します。
単に「デザインが美しい」「使いやすい」だけではなく、利用の前後に広がる感情や行動まで含まれる包括的な概念です。
たとえば、あるランニングアプリを想像してみてください。
アプリのUIがシンプルで使いやすいことはもちろん、走った距離を自動記録し、友人と共有できる機能があると「もっと走りたい」というモチベーションが生まれます。
この一連の体験こそがUXです。
人間中心設計(HCD)とUX
UXを語るうえで欠かせないのが 人間中心設計(HCD: Human-Centered Design) です。
これはユーザーのニーズや行動を中心に据えてシステムやサービスを設計する考え方です。
HCDのプロセスは次のように循環します。
| プロセス | 内容 |
|---|---|
| 利用状況の把握と明示 | ユーザーの行動、環境、ニーズを徹底的に調査する |
| 要求事項の明示 | ユーザーと組織が求めることを整理・明文化する |
| 解決策の設計 | 調査結果をもとにプロトタイプやサービスを設計する |
| 評価と改善 | 実際にユーザーに使ってもらい、フィードバックを得て改善する |
この「調査 → 設計 → 評価 → 改善」のサイクルを繰り返すことで、より良いユーザー体験が実現できます。
最終目標は 特定のユーザーと組織の要求を満たすこと にあります。
UXが重要になってきた理由
1. 企業の競争ルールが変化
かつては「どれだけ効率的に集客できるか」が競争の軸でした。
しかし、現在は 単一の企業が顧客の行動フロー全体を支援 できるようになり、使用体験を提供することが差別化要因になっています。
2. マーケティングのフォーカスが変化
「集客体験」から「使用体験」へと焦点がシフトしました。
使い続けたいと思わせる体験こそが、持続的な収益を生み出す源泉です。
3. UX人材の需要が高まる
UXデザイナー、UXリサーチャー、カスタマーサクセスといった職種の需要が急拡大しています。
ユーザー行動を深く理解し、最適な体験を設計できる人材は、あらゆる業界で必要とされています。
アフターデジタル時代とUX
「アフターデジタル」とは、リアルとデジタルが完全に融合した社会を指します。
この時代には、顧客のあらゆる行動に企業が寄り添うことが求められます。
- アプリでの購買支援
- 提案型レコメンドサービス
- 移動や探索のサポート
- SNSによる共有体験
UXは単なる「利用中の体験」ではなく、生活全体を支えるエコシステムの設計にまで広がっています。
成功事例
NIKE(スポーツ体験を一貫支援)
NIKEは、単なるシューズ販売企業から「ライフスタイルを提供する企業」へと進化しました。
具体的なUX事例は以下の通りです。
| UXの流れ | 提供する体験 |
|---|---|
| ランイベント告知 | 走るきっかけを提供 |
| シューズ購入 | 適切な製品を選ぶ体験 |
| ランニングアプリ | 距離・ペースを記録、モチベーション向上 |
| 振り返りアプリ機能 | 自分の成長を実感できる |
| SNS共有 | 仲間とのつながり・承認欲求の充足 |
この一連の体験を通じて、顧客は単に「靴を買った」ではなく、「ランニングを通じたライフイベントを楽しんだ」と感じます。
ここにUXの真髄があります。
2. Apple(シンプルさとブランド体験の統合)
AppleはUXデザインの代名詞とも言える企業です。
iPhoneやMacなどの製品自体のUIはもちろん、購入前から利用後に至るまで一貫した体験を設計しています。
- 店舗体験(Apple Store):製品を自由に試せる、スタッフが寄り添うサポート
- 製品開封体験(アンボックス体験):シンプルで洗練されたパッケージングが感動を演出
- エコシステムの一貫性:iPhone、Mac、iPad、Apple Watchがシームレスに連携
- Apple Care / サポート:不安を軽減し、長期的な顧客関係を築く
結果として、顧客は「ただのデバイス所有」ではなく、「Appleの世界観に浸るライフスタイル」を体験します。
3. Amazon(ストレスのない購買体験)
AmazonはUXを徹底的に最適化することで、世界最大級のEC企業へと成長しました。
- ワンクリック購入:最小の操作で買い物完了
- パーソナライズ推薦:過去の購買や閲覧履歴から的確に商品を提案
- 配送体験:当日・翌日配送や時間指定、プライム会員特典で利便性向上
- カスタマーサービス:返品・返金プロセスのシンプルさ
「買い物のしやすさ」だけでなく、「安心して買える」UXを実現していることが競争優位につながっています。
4. Airbnb(信頼と共感の体験設計)
Airbnbは「宿泊のUX」を根本から変えた企業です。
- 宿探しの体験:写真・レビュー・地図を組み合わせて、直感的に選べるUI
- ホストとのやり取り:チャット機能で不安を解消
- 体験型サービス(Airbnb Experiences):宿泊以外にも、現地の文化体験やツアーを提供
- 信頼性確保:レビュー制度と保証制度による安心感
Airbnbは「安い宿泊場所を探すサービス」から、「旅行そのものの体験を豊かにするサービス」へ進化しました。
企業事例まとめ表
| 企業 | UXの特徴 | 提供している体験 |
|---|---|---|
| NIKE | スポーツとアプリを融合 | ライフスタイルとしてのランニング体験 |
| Apple | 製品からサポートまで一貫 | 世界観に浸るブランド体験 |
| Amazon | シームレスな購買 | ストレスフリーで安心できる買い物体験 |
| Airbnb | 信頼性と文化体験 | 宿泊を超えた旅行全体の体験 |
こうして複数社の事例を比較すると、共通点が見えてきます。
それは「製品単体の価値ではなく、ユーザーのライフスタイル全体を支援するUX」に重きを置いている点です。
昔の企業とこれからの企業の違い
従来の企業は「ファネル型マーケティング」を採用していました。
集客を入口にし、購入で終わりという仕組みです。
しかし、今後は「使用体験(カスタマージャーニー)」を継続的に設計する企業だけが生き残れます。
| 時代 | マーケティングの焦点 | 役割が重視される部門 |
|---|---|---|
| 従来 | 集客・広告中心 | 営業・広告宣伝部 |
| これから | 使用体験・ライフサイクル提供 | カスタマーサポート、UX設計 |
つまり、広告費を大量投入するよりも、デジタルサービスを継続的に利用してもらうUX設計の方が、はるかにコスト効率よく収益を生み出せるのです。
UXとWebデザイナーの今後
これまで見てきたように、UXは「ユーザーが製品やサービスを利用して得られる体験のすべて」を意味します。
そしてこの領域は、今後ますます Webデザイナーの仕事と深く結びついていく と言えるでしょう。
かつてWebデザイナーの仕事は、サイトの見た目を美しくデザインすることが中心でした。
しかし現在では、それだけでは不十分です。
ユーザーがサイトを訪問し、情報を探し、購入や問い合わせを行い、さらにはリピート利用していくまでの 体験全体を設計する視点 が求められています。
Webデザイナーに求められるスキルの変化
| 従来のWebデザイナー | 今後のWebデザイナー |
|---|---|
| ビジュアルデザイン(配色・レイアウト・フォント) | ユーザー行動を意識した情報設計(IA) |
| HTML/CSSによるコーディング | プロトタイピングやユーザーテスト |
| クライアントの要望を形にする | ユーザーと企業の両方のニーズを調整する |
| 静的なWebサイト制作 | データ分析を活用したUX改善 |
つまり、Webデザイナーは「見た目を作る人」から「体験を設計する人」へと進化していくのです。
※IA(Information Architecture=情報アーキテクチャ)とは、「情報を整理しユーザーに分かりやすく伝える・ユーザーが情報を探しやすくする」ための手法
UX視点を持つWebデザイナーの強み
UXを理解したWebデザイナーは、ただの制作者ではなく、ビジネス全体に貢献できる人材へとステップアップできます。
- SEOとの相性が良い:UX改善は直帰率や滞在時間といったSEO指標を向上させる
- マーケティングとの連動:ユーザー体験を高めることは顧客ロイヤルティ強化につながる
- キャリアの広がり:UXデザイン、UI設計、カスタマーサクセスなど新しい領域に挑戦できる
このように、UXスキルはWebデザイナーにとってキャリアの選択肢を大きく広げる武器となります。
UXとWebデザイナーの未来
今後のWebデザイナーには、単なる「作り手」を超えて、ユーザーの体験を設計し、企業の成長を支える存在 になることが求められます。
UXを学ぶことで、デザインの質が上がるだけでなく、マーケティングやビジネス戦略にまで関わることができるのです。
つまり、これからのWebデザイナーにとってUXは「プラスアルファの知識」ではなく、生き残りに必須のスキルと言えるでしょう。
まとめ:UXは今学ぶべき必須スキル
UXは単なるデザイン手法ではなく、企業の競争力を決定づける経営戦略の一部となりました。
- 人間中心設計を繰り返すことが、ユーザーの真の満足につながる
- デジタル時代は「集客」よりも「使用体験」が価値の源泉となる
- UXスキルを持つ人材は、今後さらに需要が拡大する
営業や広告が花形だった時代から、カスタマーサポートやUX設計の時代へ。これからのビジネスで成果を出すために、UXを学ぶことは避けて通れないと言えるでしょう。
UI/UX講座および上級講座あります!個人的には上級講座の方がオススメです。
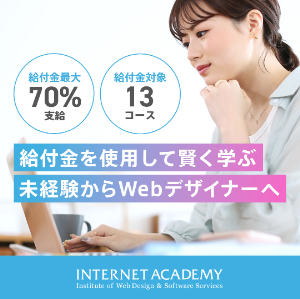
補足1:✅ UI/UXを効率的に学ぶ方法
1. 基礎理論を短期間で押さえる
- 書籍や講座で「UIデザインの原則」や「UXプロセス」をまとめて学ぶ
- 代表的なフレームワークを知る
- UIの原則:近接・整列・反復・対比(ノンデザイナーズデザインブック)
- UXの流れ:調査 → 設計 → プロトタイプ → テスト → 改善
- 📚 おすすめ教材
- 『ノンデザイナーズ・デザインブック』
- 『UXデザインの教科書』
- Udemyの「UXデザイン基礎入門」
👉 1〜2週間で基礎知識をインプット → 実務で使いながら深めるのが効率的です。
2. 良いデザインを観察・模写する
👉 実際に手を動かして再現することが最大の学習効率化になります。
3. 小さなプロジェクトでユーザー視点を体験する
- 例:
- 自分のポートフォリオサイトをリニューアル → 友人に使ってもらいフィードバック
- 架空サービスのアプリUIをFigmaで設計 → テストユーザーに操作してもらう
- 「自分が思った通りに動かない」→「なぜ使いにくいのか」を考えるプロセスがUX学習の核心。
4. ツールを使いながら学ぶ
- Figma:UI設計とプロトタイピング
- Adobe XD:インタラクションデザイン(Creative Cloud Pro)
- Miro / FigJam:ユーザーフローやジャーニーマップ
- Insight Journey:解決したい課題と課題を抱えているターゲットを入力すると、仮説を立ててくれる。
- Google Analytics / Hotjar:実際のユーザー行動を分析
👉 ツールに触ることで「机上の空論」が「実務で使える知識」に変わります。
5. UI/UXを意識したアウトプット習慣
- 作ったサイトやデザインに対して
- 「このUIはユーザーにとって直感的か?」
- 「UXとしてストレスなくゴールにたどり着けるか?」
- → 自分でレビューシートを作ると学習効率が爆上がり。
6.効率的に進めるポイント
- 知識は短期でインプット → 作品で実践しながら吸収
- 模写やリデザインを通じて「なぜ?」を考える癖をつける
- ユーザーテスト(小さくてもOK)で実際の声を反映する
👉 要は「本で勉強 → 手を動かす → ユーザー視点で検証」を高速で回すのが効率的です。
※補足ですが、UI/UXは資格よりポートフォリオや実践経験が評価されやすい分野です。
「UI/UXの勉強=ポートフォリオ改善」と直結させるのがベストですよ。
補足2:✅ UI/UXチェックリスト(ポートフォリオ用)
「会社所属を目指すWeb制作者」が ポートフォリオでUI/UX力をアピールできるチェックリスト をご用意しました。
これは採用担当や制作会社の現場が見て「おっ、この人はユーザーを意識しているな」と思われるポイントに絞っています。
1. 視認性(見やすさ)
- 文字サイズは十分大きいか?(最低16px以上)
- 見出しと本文の階層が明確か?(H1〜H3の使い分け)
- 行間や余白で詰まりすぎないデザインになっているか?
- 色のコントラストが十分か?(背景と文字が読みやすい)
2. 操作性(使いやすさ)
- ナビゲーションがわかりやすく配置されている(ヘッダー or ハンバーガー)
- リンクやボタンは十分なクリック領域がある(タップでも操作しやすい)
- 「戻る」「次へ」などの操作が直感的にできる
- フォームは入力しやすく、必須項目がわかりやすい
3. 一貫性(統一感)
- 色やフォントが全ページで統一されている
- ボタンやリンクのスタイルが一貫している
- 画像サイズや比率が揃っている
4. レスポンシブ対応
- PC・タブレット・スマホでデザインが崩れない
- モバイル時のメニューが使いやすい(ハンバーガー、スワイプ対応)
- 画像が画面幅に合わせてリサイズされる
5. ユーザー導線(UX視点)
- 最初に「何のサイトか」がひと目でわかる
- ボタンやリンクに「行き先」が明確に示されている(例:詳しく見る → サービス詳細へ)
- CTA(お問い合わせ・応募など)が自然な位置にある
- 不要なクリックやスクロールを強要していない
6. 信頼性
- お問い合わせ先やSNSリンクが明確
- ダミーテキストではなく、実際に意味のある文章を配置
- プロフィールや経歴が整理されている
- セキュリティ面を意識(https化、外部リンクにtarget=”_blank” + rel=”noopener”)
まとめ:アピールにつながる工夫
- Before → After のUI改善例を載せる
→ 「改善前はこうで、改善後にこう工夫した」と説明すると説得力大。 - 制作物ごとに「意識したUI/UXポイント」を1〜2行で添える
→ 例:「フォーム入力時にエラー内容が即表示されるよう工夫しました」
このチェックリストをポートフォリオに反映すると、ただ「作れる」だけでなく「ユーザーを意識して設計できる」 人材だとアピールでき有効です。
補足3:✅ ポートフォリオ自己紹介文(UI/UXアピール入り)
パターン①:シンプル&誠実系
はじめまして、〇〇と申します。
Web制作においては、単に見た目を整えるだけでなく、ユーザーにとって見やすく、使いやすいデザインを意識しています。
特に、ナビゲーションの分かりやすさやフォームの入力しやすさなど、UI/UXの観点から改善を重ねることを心がけています。
今後も「ユーザーが迷わず目的を達成できるWebサイト」を目指して制作に取り組んでまいります。
パターン②:改善事例を強調(即戦力アピール)
Web制作に携わる中で、「見た目」よりも「使いやすさ」こそがサイトの価値を高めると考えています。
例えば、ポートフォリオ作品ではフォーム入力時にリアルタイムでエラーメッセージを表示する仕組みを導入し、ユーザーがスムーズに送信できるよう工夫しました。
このように、小さな改善の積み重ねがユーザー体験の向上につながると考え、制作を行っています。
パターン③:UX全体を意識(マーケティング志向)
Webサイトは「ユーザーの行動をサポートするツール」と考えています。
そのため、デザインやコーディングの際には、見やすさ(UI)と目的達成までのスムーズな導線(UX) を常に意識しています。
また、SEOやアクセス解析の知識も学んでおり、ユーザーが求める情報に最短でたどり着けるWebサイトを目指しています。
バージョン④(シンプル)
私はWeb制作において、デザインやコーディングの美しさだけでなく、「使いやすさ」と「伝わりやすさ」を常に意識しています。
文字サイズや配色のコントラスト、レスポンシブ対応など基本的なUIはもちろん、ユーザーが迷わず目的の情報にたどり着ける導線設計を心がけています。
バージョン⑤(改善事例をアピール)
Webサイト制作の際には、UI/UXの改善に重点を置いています。
例えば、フォーム入力画面ではエラー内容をリアルタイムで表示することで、ユーザーがストレスなく操作できるよう工夫しました。
また、スマートフォンでの操作性を考慮し、クリック領域やナビゲーションの配置を最適化するなど、小さな改善を積み重ねています。
バージョン⑥(採用担当に響く実務寄り)
私はWeb制作を学ぶ中で、「見た目のデザイン」だけではなく、「ユーザーが快適に利用できる体験」を重視してきました。
制作物ごとに「どのような課題を解決するUIなのか」を意識し、サイトに訪れた方が迷わず目的を達成できるよう設計しています。
こうしたUI/UXへのこだわりは、SEOやコンバージョン率の改善にも直結すると考えており、実務においても成果につなげていきたいです。
まとめ:っとまぁ、こんな感じで切り出すとオリジナリティあっていいよというお話
最近のポートフォリオって、無難なデザインが多いのでもう少し冒険してもいいと思うんですよ。
未経験者に完璧なことは求めてないんで、尖った感性とかないならこだわりを見せて欲しいのが本音です。
スクールで作ってきたのを少し変えるんじゃなくて、そこにこだわりをプラスすると色々変化が出せるので。
長々と書きましたが、+1の個性をくっつけて作るとウケが良いですよというお話でした。
40代という題名ですが、ロードマップ(スキルセット)も載せているので是非読んでください。